2024年(令和6年)の国民生活基礎調査の結果が発表されましたね。この調査は、保健、医療、福祉、年金、所得など、国民生活の基礎的な事柄を明らかにし、厚生労働省の政策立案に役立てられています。
2024年 国民生活基礎調査:日本の世帯状況
最新の統計によると、2024年の日本の総世帯数は約5,482万世帯です。内訳を見てみましょう。
- 高齢者世帯: 1,720万世帯(全体の31.4%)
- 母子世帯: 59万世帯(全体の1.1%)
- 児童のいる世帯: 907万世帯(全体の16.6%)
高齢者世帯が全体の3割以上を占める一方、母子世帯が1.1%というのは、もしかしたら多くの方のイメージと異なるかもしれませんね。
世帯の所得状況
気になる世帯の所得状況ですが、以下のようになっています。
- 1世帯当たりの平均所得金額: 536万円
- 高齢者世帯の平均所得金額: 314.8万円
- 児童のいる世帯の平均所得金額: 820.5万円
児童のいる世帯の平均所得が820.5万円と高いのは、2024年の日本の平均年収が426万円であることを考えると、夫婦共働きによる所得が大きく影響していると考えられます。
世帯の可処分所得
所得から税金や社会保険料を差し引いた可処分所得は、以下の通りです。
- 1世帯当たりの平均可処分所得金額: 415.6万円
- 高齢者世帯の平均可処分所得金額: 266.7万円
- 児童のいる世帯の平均可処分所得金額: 621.5万円
税金・社会保険料の負担
「ちょっと待ってください!」と思わず声が出そうなのが、税金・社会保険料の負担額です。
- 1世帯平均: 120.4万円(所得に対する控除率:22.5%)
- 高齢者世帯平均: 48.1万円(所得に対する控除率:15.3%)
- 児童のいる世帯平均: 199万円(所得に対する控除率:24.3%)
特に、児童のいる世帯、つまり現役世代の負担額と控除率が他と比べて高いことがわかります。これだけの負担があると、生活が苦しいと感じるのも無理はありません。少子化の一因とも考えられるこの現状は、私たちの社会にとって大きな課題です。
生活意識の推移
世帯別の生活意識を見ると、前述の負担が如実に表れています。
全世帯
- 苦しい: 58.9%
- 普通: 36.5%
- ゆとりがある: 4.6%
高齢者世帯
- 苦しい: 55.8%
- 普通: 40.1%
- ゆとりがある: 4.2%
児童のいる世帯
- 苦しい: 64.3%
- 普通: 30.4%
- ゆとりがある: 5.1%
児童のいる世帯で「苦しい」と感じている割合が最も高く、現役世代が直面している厳しい現実が伺えます。
まとめ
今回の国民生活基礎調査の結果からは、現役世代の6割以上の世帯が生活に苦しさを感じているという厳しい現状が浮き彫りになりました。彼らは金額的にも比率的にも高い税金や社会保険料を負担し、社会全体を支えています。
この統計は、日本における「シルバー民主主義」という言葉を想起させるかもしれません。数の多い世代に有利な政策がとられがちになるのは、民主主義の性質上避けられない側面もあります。
2025年の参議院選挙は終わりましたが、私たち一人ひとりがこの国の現状を正しく理解し、将来を見据えた判断をすることが、より良い社会を築くために不可欠だと考えさせられますね。

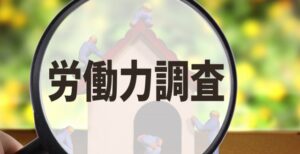
コメント
COMMENT