「賃上げ」を叫ぶのは誰の役割?
近年、政府や政治家が「賃上げ」を繰り返し訴えています。
しかし、私はそのたびに違和感を覚えます。
なぜなら、実際に賃金を上げるのは行政ではなく企業だからです。
もちろん、賃上げ促進のために各種助成金や税制優遇などの政策が講じられているのは理解しています。
しかし、最終的に賃金を上げるかどうかを決めるのはあくまで企業であり、政治の号令だけでは賃金は上がりません。
「失われた30年」と言われる日本の賃金
日本では「失われた30年」と呼ばれ、賃金の伸び悩みがよく指摘されます。
内閣府のデータによると、1991年を100としたとき、2020年の名目賃金は100.1、実質賃金は103.1。
確かにこの数値だけを見れば、日本の賃金はほとんど伸びていないように見えます。
実は労働時間は減っている
しかし、違う角度から見てみると、少し違った実態が見えてきます。
厚生労働省の「労働時間の推移に関する考察」によると、
-
男性の平均労働時間は1990年の約52時間/週から2023年には約43時間/週へ
-
女性は約41時間/週から約32時間/週へ
と、それぞれ労働時間が大幅に減少しています。
背景には、男性では労働時間そのものの短縮、女性ではパートタイム労働者の増加があります。
実際にパート労働者数は、1990年の約722万人から2025年には1,020万人に増加しています。
賃金が横ばいでも「実質的には上昇」している?
つまり、働く時間が減っているにもかかわらず賃金水準が横ばいということは、
時間あたりで見ればむしろ賃金は上昇している可能性があります。
かつての日本では「企業戦士」と呼ばれたサラリーマン像が象徴的でした。
週休1日、夜遅くまでの残業が当たり前で、家庭では専業主婦が家計を支える時代。
それが今では「パワーカップル」という言葉に代表されるように、共働きが当たり前になっています。
また、女性のパート就労によって家計を補う世帯も増えています。
賃上げが「実感できない」もう一つの理由
さらに忘れてはならないのが、賃上げに伴う控除の増加です。
社会保険料や所得税、住民税などが増えることで、手取り額(可処分所得)は同額の上昇を実感しにくい構造になっています。
「給料は上がったのに生活は楽にならない」という声の背景には、こうした仕組みがあるのです。
まとめ:本当に必要なのは「賃上げ」だけではない
今回の考察は、内閣府や厚生労働省の公表データをもとにしています。
確かに賃上げは重要ですが、単に賃金を上げるだけでは、豊かさの実感にはつながりません。
労働時間の短縮、共働きの普及、税・社会保障制度などを総合的に見直すことで、
初めて「実質的な生活の向上」が実現するのではないでしょうか。
政府には、賃上げだけでなく、より実効性のある景気・生活支援策を期待したいところです。

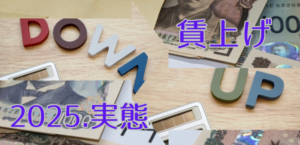
コメント
COMMENT